「うちの子、お金の使い方が雑すぎて不安…」
「でも投資なんてまだ早い?いやいや、でも将来が心配…」
そんな風に感じているあなた。実は今、金融教育は“待ったなし”の時代に突入しています。
今回は、投資初心者の親でもできる!
中学生・高校生の子どもと一緒に学ぶ「お金の増やし方」について、体験談&実践法を交えて解説していきます😊
- 第1章:金融教育はもう学校でも始まっている!?
- 第2章:「投資はギャンブル」って思ってる中高生、多すぎ問題
- 第3章:「何から始めれば?」に答える家庭での金融教育ステップ
- 🔍用語解説コーナー
- 第4章:「うちの子にはムリ」と思う前に知ってほしいこと
- 第5章:未来に差がつく!今からできる3つの家庭習慣
- まとめ
- カツくんの一言コーナー
第1章:金融教育はもう学校でも始まっている!?
実は2022年から、日本の高校家庭科では「資産形成」が正式に授業に登場しました。
NISAやiDeCoの概要まで教えるんです!すごくないですか?😳
文部科学省の学習指導要領によれば、「ライフプランと資産形成」がカリキュラムの一部に加わり、
“家計管理・貯蓄・投資・保険”など、実生活に密着したテーマが扱われるようになりました。
でも…授業は1〜2時間で終わり。しかも進学校では飛ばされることも…😓
要するに、家庭の教育が超重要なんです!
カツくん:
ワイの頃は“お金の話=はしたない”って思われとったけど、
今は「話さないほうがリスク」やねんで〜💦
第2章:「投資はギャンブル」って思ってる中高生、多すぎ問題
突然ですが、あなたのお子さんは「株ってギャンブルでしょ?」と言ったことありませんか?
実際、文科省の調査では中高生の約6割が「投資は危険」と回答しています。
原因はシンプルで、「知識がない=怖い」から。
でもそれって、刃物は危ないから包丁を持たせないって言ってるのと同じかも…?
正しい知識を与えれば、お金も“使える道具”になるんです🍳💰
我が家では、「投資信託って何?」「NISAってなんで非課税?」など、
家庭内クイズ形式でゲーム感覚にして伝えました🎮
カツくん:
ちなみに息子に「お金が勝手にふえる魔法やで」って言ったら、
「え、凄〜い」って笑ってた(笑)
第3章:「何から始めれば?」に答える家庭での金融教育ステップ
では、実際に何から始めればいいのか?以下の3ステップがオススメです👇
① おこづかいの管理を本人に任せる
・固定額制 or 成果報酬型(お手伝いなど)
・「使う・貯める・増やす」の3区分で管理する
・失敗もOK!それが学びになる✨
② 予算会議を一緒に開く
・修学旅行・部活道具など、将来の支出を子どもと一緒に計画する
・「欲しいもの vs 必要なもの」の対話が超大事
③ ジュニアNISA・家族NISAを使った実践型学習
・親のNISA口座を一緒に確認する
・「投資信託って何に連動してるの?」を解説する
・1,000円分の運用結果を“おこづかい”として可視化!
学校では教えてくれない「実践ベースの金融教育」こそ、家庭でこそできる最大のギフトなんです🎁
🔍用語解説コーナー
金融リテラシー:
「お金に関する基礎知識と活用力」のこと。
収入・支出・貯蓄・投資・リスクなどを理解して適切な行動を取る力。
ジュニアNISA:
2023年末で終了した未成年向けの非課税投資制度。
現在は保護者の新NISA口座で学ばせるのが一般的。
投資信託:
多くの投資家から集めた資金を、専門家が複数の株や債券に分散投資してくれる商品。
第4章:「うちの子にはムリ」と思う前に知ってほしいこと
「でもウチの子、数学苦手だし…」「投資とか理解できるの?」
そう思う気持ち、よ〜く分かります。
でも実は、金融教育に必要なのは“計算力”じゃなく「思考力と会話力」なんです💬
・お金の価値を「時間」として考える練習
・広告にだまされない“判断力”
・「なんでこの価格なんだろう?」という好奇心
つまり、「なぜ?」と問いを持つクセこそが最高の金融教育!
正解を教えるより、一緒に考える環境が大切です。
第5章:未来に差がつく!今からできる3つの家庭習慣
- 📅 ① 毎月「家族予算会議」を開催する
今月の支出・貯金・来月の目標を共有しよう! - 📈 ② 月1回「家庭ファンド運用報告会」を実施
子どもが“出資者”になる感覚を味わえる - 📚 ③ お金の絵本やマンガを一緒に読む
『ドラえもんの経済マンガ』『お金の教科書』シリーズは特におすすめ!
ちょっとしたことから始めるだけでも、子どもは驚くほど吸収していきます。
今日からできること、きっとあるはずですよ😊
まとめ
金融教育は、何も特別なものではありません。
会話の中にヒントがあり、買い物の中に学びがあります。
「まだ早い」「ウチの子には無理」と思う前に、
まずは「お金の話をしてもいい空気」をつくるところから始めてみましょう。
将来、子どもが困らないために。
今日から一緒に、“お金と仲良くなる練習”を始めませんか?✨
カツくんの一言コーナー
カツくん:
お金って、知れば知るほど“味方”になるもんやで。
せやからこそ、子どもと一緒に学ぶ姿を見せるのが一番やと思うんよ😊
🌍コラム:日本と海外の金融教育の差、知ってますか?
実は、日本の金融教育は「かなり遅れている」と言われています。
OECD(経済協力開発機構)の調査によれば、金融リテラシーの国際比較で日本は下位グループ。一方、先進国ではすでにこんな教育が進んでいます👇
- 🇺🇸アメリカ:州によっては高校で“必修科目”として投資・ローン・クレカの知識を学ぶ
- 🇬🇧イギリス:小学校から「生活に必要なお金の扱い方」を家庭科に統合
- 🇸🇬シンガポール:金融機関と連携し、子ども向けの金融体験イベントを開催
日本も少しずつ追いつこうとしていますが、やはり「家庭の教育」がカギ。
世界と比べても、親の関わりが子どもの未来を左右する時代になっています📊
🧠コラム:あなたの中の“お金ブロック”、残ってませんか?
親世代の多くは「お金の話=なんとなく恥ずかしいもの」という価値観で育ってきましたよね。
でも今、それが子どもの成長の足かせになる可能性があるんです。
お金を語ることは、人生をどう生きたいかを考えること。
収入・支出・投資・貯蓄を通じて、「どうしたいか」「何を優先するか」を学べる最高の教材なんです📚
この価値観を変えるには、こんな習慣がおすすめ👇
- 📕 まずは自分が「お金の勉強」を始めてみる
- 📣 お金の話を“ポジティブな会話”に変える
- 👪 家族に「家計シェア」をちょっとだけ見せてみる
「見せること=教えること」。
最初の一歩は、あなたからです✨
📉コラム:貯金しても減る時代に、どう教える?
「コツコツ貯めれば大丈夫」
そんな時代は、残念ながら終わりに近づいています。
2024年、日本のインフレ率は前年比+2〜3%の推移を見せました。
つまり、「銀行に100万円を預けたら、実質97万円になる」ようなもの。
だからこそ、子どもにも“お金の増やし方”を学ばせるべき時代なのです。
💡家庭でできる“インフレ時代の教育法”3選
- 🧠「なぜ物価が上がるのか?」をニュースで一緒に考える
- 📈「投資=働かなくても稼げる」ではなく「仕組みを使う」と教える
- 🍞「同じ500円で買えるものが減った」実体験を共有
投資信託やNISAの内容はさておき、お金の“目減りリスク”を実感させることが、最初の学びになります。
カツくん:
昔は「1万円あれば何でも買えた」って言ってたけど、
今はコンビニで2〜3品で終わりやもんね…😇
リアルに感じさせるって、やっぱ大事やわ〜!
🧓コラム:親が知らないお金、子どもはどう学ぶ?
「子どもにはちゃんとした“お金の知識”を持ってほしい」
そう願うのは親心。でもちょっと待ってください。
あなた自身、「お金」について自信を持って説明できますか?
・NISAってどう使う?
・インフレってどういう仕組み?
・保険と投資の違いって?
実は、親の金融知識レベル=子どもの学習限界になりがちなんです。
学校では基礎しか触れません。だからこそ、「一緒に学ぶ姿勢」が一番大事。
- 👪「一緒にニュースを読む」
- 📺「TV番組やYouTubeで“お金解説”を見る」
- 📚「親も学び直す」
完璧じゃなくていいんです。
“分からないからこそ、勉強してる姿”を見せることが、最高の金融教育です✨
🎓コラム:奨学金は“助け”じゃなく“借金”である
高校生が大学進学を考えたとき、避けて通れないのが「奨学金」。
進学時に約半数の学生が利用する現実があります。
でも、奨学金の“本質”を親子でちゃんと話していますか?
実はこれ、「人生で最初に出会う借金」なんです。
● 返済は社会人になってから20年近く続くことも
● 年間で数十万円の利息がつくケースも(有利子)
● 退職金を充てて返済する例も…😨
「借金=悪」ではなく、「借金=責任と管理が必要なもの」だと
高校生のうちに話せるかどうかで、未来が変わります。
奨学金を使わずに進学する選択肢、給付型との違い、費用対効果。
今こそ「教育費と金融教育」をセットで考えるタイミングかもしれませんね。
📱コラム:子どもの“課金”は、怒るより学びに変える!
中高生の「スマホ課金問題」、家庭内トラブルの定番ですよね😓
「勝手に課金した」「月額引き落としに気づかなかった」など、よく聞きます。
でも、ここにこそ金融教育のチャンスがあります!
🧠課金トラブルを“学び”に変える3ステップ
- ① 契約・サブスクの仕組みを一緒に確認する
「最初の1ヶ月無料」などの仕掛けを親子で“仕組み理解” - ② 家計目線で考える体験をさせる
「月1,000円のゲーム課金=年1.2万円」と見せて、価値を可視化! - ③“責任ある消費者”として扱う
ルールを決めて任せると、子どもも“自分で考える力”がつく
怒るだけでは、課金=“バレなきゃOK”の裏ルールに💣
逆に、ちゃんと話し合えば、家計の管理者の第一歩にもなります😊
👛コラム:高校生のバイト代、どう使わせる?3分割ルールで管理習慣を育てよう!
高校生になるとアルバイトで月数万円の収入を得る子も増えてきます。
でもそのまま“使いたい放題”になっていませんか?💸
そこでおすすめなのが、「3分割ルール」です!
- ① 使う:50%
好きなものを買ったり遊んだり、人生を楽しむ部分 - ② 貯める:30%
修学旅行や進学準備、自転車の買い替えなどの「目標貯金」 - ③ 増やす:20%
親と一緒に“投資信託”で運用体験。毎月1,000円でもOK!
この方法なら「バイト代=すぐ消えるお金」ではなく、“お金の使い道にはバランスが必要”という感覚が育ちます😊
カツくん:
ワイも高校生の頃、ゲームに月5,000円突っ込んで後悔したなぁ…
あの時ちょっとでも「貯める習慣」あったら、もっと違ったかも💦
💳コラム:クレカより安全!子ども向けキャッシュレス教育には“デビットカード”が最適
最近は「子どもに現金を持たせたくない」「スマホ決済に慣れさせたい」という家庭も増えています。
そこで注目されているのが“子ども向けデビットカード”の活用です📲
🟢 デビットカードが教育に向いている理由
- 🔐 銀行口座と直結で、残高以上は使えない=安心!
- 📊 利用履歴がアプリで確認でき、“見える化”教育に◎
- 🧠「使ったら減る」をキャッシュレスで体感できる
📌 実際に使えるサービス例
- ・みんなの銀行(15歳〜利用可)
- ・LINE Payプリペイド(保護者管理機能あり)
- ・楽天銀行ジュニアデビット(13歳〜)
「キャッシュレス=便利」だけではなく、「お金の管理力が必要」という感覚を育てるなら、デビットカードはかなり有効です💡
👨👩👦コラム:家庭で“家計会議”やってみた!リアルな会話例と学びの気づき
「家計の話を子どもにしていいの?」という声、多いです。
でも実際にやってみたら…めっちゃ良かったんです!
● カツ家の“月1家計会議”の流れ
- ① 今月の出費をざっくり共有
(例:「電気代が高かった!ゲームつけっぱなしかも?」) - ② 来月の目標を一緒に決める
(例:「おやつ代1,000円以内チャレンジする?」) - ③ ちょっとした“ごほうび制度”を入れる
(例:「目標達成したら好きなケーキ買おう🎂」)
子どもも自分ごとになると、行動が変わってくるんですよね!
「家計=親の仕事」ではなく「家族のプロジェクト」にすると、グッと楽しくなります😊
カツくん:
実はワイの息子、最近「うちの水道代いくらなん?」って聞いてきたで…
一緒にアプリ見ながら「これはお風呂長すぎやろ」ってツッコまれた(笑)

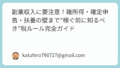
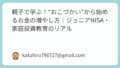
コメント