「おこづかいって、いくら渡すのが正解?」「子どもに“投資”を教えるなんて早すぎる?」
そんな疑問を抱えたこと、ありませんか?📚
近年、日本でも「金融教育」が注目を集めています。2022年から高校家庭科では「資産形成」まで教える時代に突入し、親世代も“教える力”を試される場面が増えてきました。
この記事では、実際に3歳の息子と暮らす筆者が、「おこづかいから始めるお金の増やし方教育」をテーマに、ジュニアNISAや家庭内ファンドなども交えてリアルに解説していきます。
「お金の教育、何から始めたらいいの?」という初心者の方でも安心して読める内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください😊
第1章:日本でも始まった「金融教育」義務化の波🌊
2022年、日本の高校教育において「資産形成」という言葉がついに教科書に登場しました。これは家庭科の授業で「人生設計と家計管理」の一部として、投資信託・NISAなども扱われるようになったことを意味します。
かつては「お金の話=はしたない」とされがちだった日本。しかし、物価上昇や年金不安を背景に、お金の知識はもはや「必修科目」です。
では、義務教育よりも早く、家庭でできる金融教育とは何でしょうか? その第一歩が「おこづかい」なのです。
カツくん:
昔は「投資ってギャンブルやろ?」なんて思ってたけど、今や教科書に載る時代やで…💦
子どもにこそ“ほんまのお金の使い方”教えてあげなあかんね!
第2章:おこづかい制で学ぶ「使う・貯める・増やす」
「おこづかい制」は、子どもにとって最初の“家計管理体験”です。単に好きなものを買うためだけでなく、「予算管理」「自己決定」「優先順位」を学ぶチャンスでもあります。
我が家では以下のルールでスタートを考えています👇
- 5歳:お手伝い報酬制(10円〜100円)
- 6歳〜:定額制(月300円)+目標貯金
- 貯めたお金の一部は「親ファンド」で運用体験!
子どもは「お金を使う」だけでなく、「貯める」「増やす」を体験することで、将来の金融リテラシーの土台を作っていきます。
第3章:カツ家のリアル!3歳児の“お金ルール”実例
我が家の3歳児とのお金ルールを紹介します。最初はコインを貯金箱に入れるだけでしたが、徐々にこんなやり取りが生まれました。
👦「これ買いたいけど、どいしたらいいの…」
👨「じゃあ、もう少しお手伝い頑張ってみる?」
こんな会話を通じて、「お金は努力で得られる」という感覚が芽生えてきたのです。お金の価値を“体感”で理解させるには、現金を扱わせることが何より効果的です。
第4章:親子で投資を学ぶ「ジュニアNISA」の活用法
現在は新NISAに一本化されていますが、以前の「ジュニアNISA」を活用して、我が家ではこんな教育を実践してきました。
- 子ども名義で口座を開設(親が代理管理)
- 「投資信託って何?」を絵本やアニメで学ぶ📚
- 一緒に毎月1,000円ずつ“未来のおもちゃ代”として投資体験
値動きを見せて「今は下がってるけど、また上がることもあるんだよ」と説明すると、ゲーム感覚で関心を持ち始めます。
お金の用語解説:金融教育/ジュニアNISA/リスクとリターン
金融教育:
「お金の価値・使い方・増やし方」を学ぶ教育。2022年から高校で必修化され、社会で生きる力として重要視されています。
ジュニアNISA:
20歳未満が利用できた非課税投資制度(2023年末で終了)。現在は「未成年でも保護者が新NISAの活用を検討する」など実践的な対応が求められています。
リスクとリターン:
リスク=危険ではなく「価格変動の幅」。リターン(収益)とのバランスを取って、資産形成を考える考え方です。
カツくん:
せやけど子どもに「投資しなさい」と言うんやなくて、
一緒に“観察”することから始めたらええんやで♪📊
第5章:「家庭ファンド制度」とは?ゲーム感覚でお金教育
我が家では“家庭ファンド制度”と呼ばれる仕組みを導入中です。ルールはこうです👇
- 親が“ファンドマネージャー役”
- 子どもが“投資家役”としてお金を預ける
- 親が投資先(米国株インデックスなど)を実際に運用
- 年に一度“分配金”として報告+報酬おやつ🍩
ゲームのような感覚で、「お金を使わずに増やすってどういうこと?」を学ばせることができます。
第6章:「投資は危ない?」子どもに伝えるべき本質
「投資=危ない」「お金=汚い」というイメージを持っている大人は少なくありません。ですが、本当の危険は「知らないこと」です。
だからこそ、家庭内で「一緒に考える」「一緒に調べる」姿勢が大切なんです。
子どもは、親の行動をよく見ています。
親が“考えて使う”“考えて増やす”姿を見せることで、お金とどう向き合うかを学んでいくのです。
まとめ
今回は、「親子で学ぶお金の増やし方」として、おこづかいから始まる金融教育、そしてジュニアNISAや家庭ファンドの実践について紹介しました。
資産形成は、決して「大人になってから」始めるものではありません。子どもと一緒に、小さく始めて、小さく失敗する中で、「お金に強い人間力」を育てていきましょう😊
カツくんの一言コーナー
カツくん:
お金の話って、親が苦手やと子どもも苦手になりがちやで💦
せやからこそ、一緒に学べる“家庭ファンド”とかめっちゃええで!
「増やし方」を教えるって、めっちゃ愛情やと思うわ😊
💡コラム:おこづかいの金額っていくらが正解?
おこづかいを渡すとき、まず悩むのが「金額」ではないでしょうか。
実はこのテーマ、文部科学省や各種金融機関も定期的に調査しており、以下のような傾向が見られます。
| 年齢 | 平均月額 | 支給方法 |
|---|---|---|
| 5〜6歳 | 100〜300円 | お手伝い報酬型 |
| 小学校低学年 | 300〜500円 | 定額+ごほうび制 |
| 小学校高学年 | 500〜1,000円 | 週ごと・月ごと制 |
| 中学生 | 1,000〜3,000円 | 月額定額制 |
| 高校生 | 3,000〜5,000円 | +昼食代や交通費を別支給 |
重要なのは「金額」よりも“ルールと目的”を明確にすることです。
例えば「月1,000円だけど、無駄遣いしなかったら+ボーナスあり」など、ゲーム性を持たせるのも効果的です🎮✨
📊コラム:家庭ファンドの作り方|実践ステップ解説
家庭ファンドとは、家庭内で“お金の運用体験”をシミュレーションする教育法です。以下の流れで始めてみましょう。
- 親がファンドマネージャーを宣言する(笑)
「お父さん/お母さんは今日から“カブ先生”や!」と、ちょっとした演出が子どもにはウケます。 - おこづかいの一部を「投資資金」として預かる
子どもに選ばせるのも大事。「100円をファンドに入れる?それとも貯金箱に入れる?」と問いかけてみてください。 - 月1回「運用報告会」や「収益ランキング」開催
「今月は●●円ふえました!お祝いのプリンどうぞ🍮」など、体験型で楽しませると習慣になります。
ここで大切なのは、損益の結果を責めないこと。リスクや市場変動を“体験”させることが一番の学びです😊
⚠️コラム:なぜ“投資=危険”と思ってしまうのか?
子どもに投資を教えるとき、多くの親がブレーキをかけてしまうのが「投資って危なくないの?」という不安。
でも実は、その“不安”の多くは教育不足や過去の失敗体験に起因しています。
代表的な「投資=危険」思考の原因は以下の3つ👇
- ①「元本保証がない」=損をするものと勘違いしている
➡️ 銀行預金と比較するが、インフレで価値が目減りすることは考慮されていない - ②「過去に大損した知人の話」が記憶に残っている
➡️ FXや仮想通貨などの投機性の高い投資とごっちゃになっているケースが多い - ③「数字が苦手」という心理的ブロック
➡️ 難しそうだから手を出さない、という防衛反応が働く
大人が投資を“敵視”していると、子どもも同じように受け止めてしまいます。
「ちゃんと学べば怖くない」「怖さを理解してこそ大人」と伝えることが、親の役割なのかもしれませんね✨
💳コラム:キャッシュレス時代に“現金おこづかい”は時代遅れ?
最近では、子どものおこづかいも「電子マネー」や「プリペイドカード」で管理する家庭が増えています。
ただし、いきなりキャッシュレスに移行するのはおすすめしません。
理由は簡単。“お金が減る感覚”をつかみにくいからです。
スワイプやピッだけで買い物が完了してしまうと、「支出=見えない」という錯覚に陥りやすくなります。
我が家では、次のように段階的に進める方法を取り入れています👇
- ① 3〜6歳:現金おこづかいで“お金の存在”を実感
- ② 7〜10歳:ICカードのチャージを親と一緒に体験
- ③ 小5以降:プリペイド式のおこづかいカード導入(決済通知あり)
「目に見える→見えないお金」への橋渡しが親の役目!
アプリを使って一緒に残高チェックをするのも楽しいですよ😊📱
🗣️コラム:子どもに“家計の話”をどこまでするべきか?
「お金の話は子どもにするべきじゃない」
こんな価値観、まだ根強くありませんか?👀
確かに、大人の不安をそのまま子どもにぶつけるのはNGです。
でも、お金について話さない=学ぶ機会を奪うことにもなりかねません。
おすすめは「家庭マネー会議」の定期開催✨
月に1度、次のようなテーマで“家族会議”をしてみてください。
- ・今月の食費や光熱費、どうだった?
- ・来月はどんな支出がある?
- ・旅行・おでかけの予算を一緒に決めよう!
- ・家庭ファンドの“運用報告会”🎉
会話の中で「我が家は〇〇万円の予算でやりくりしてるよ」といったリアルな数字が出てくるだけでも、経済感覚の種まきになります。
「お金=オープンに話していいこと」
まずはその空気をつくることが、将来の金融リテラシーにつながります😊
📚コラム:親子で楽しむ「お金の絵本&アニメ」厳選5選
「お金の教育って、どうやって教えたらいいか分からない…」
そんな方におすすめなのが、“物語”で伝えるマネー教育です。
以下は実際に我が家で使って反応がよかったコンテンツたち👇
- 『あったらいいな おかねのほん』(PHP研究所)
→「お金って何?」をやさしく説明してくれる幼児向け絵本 - 『おかねってなぁに?』(サンマーク出版)
→小学低学年におすすめ。貯金と消費を楽しく学べる - 『ミッフィーといっしょに おかいもの』(福音館)
→かわいくて親しみやすい!お買い物ごっこの導入にも◎ - NHK for School「おかねのがっこう」
→動画で学べる公的教育コンテンツ。小学生向けにぴったり - 『ドラえもん 学べるシリーズ:お金と経済のひみつ』
→中学年〜高学年向け。仕組みや税金についてもカバー!
“見る・読む・体験する”の3ステップで、子どもの理解はぐんと深まります📈
親も一緒に読んで「なるほど〜!」と感心しちゃいますよ✨
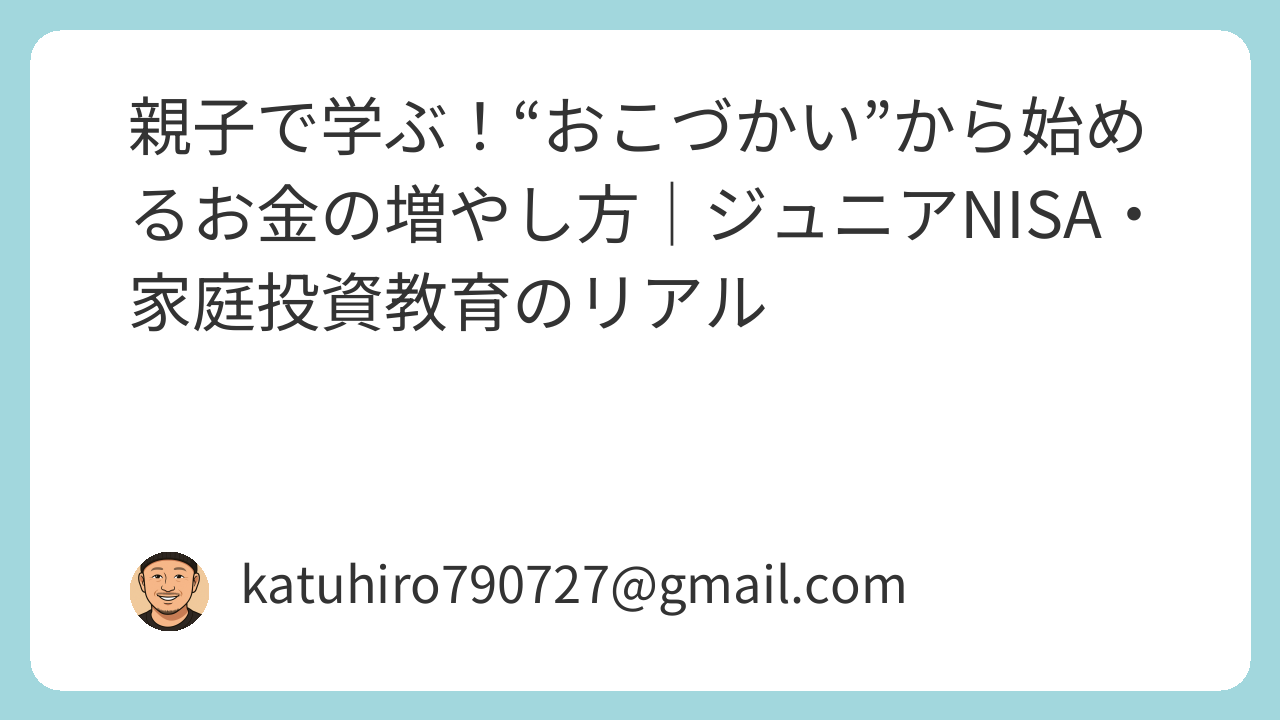
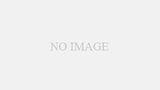

コメント