「団信があるから、万が一のことがあっても大丈夫だよね?」
これは、僕が35歳のときに初めて住宅ローンを組んだとき、銀行の担当者から言われた言葉です。
そして僕自身も「なるほど、団体信用生命保険(団信)ってすごいな」と、なんとなく安心していたんです。
でも、その数年後──。
実家の父が倒れたとき、住宅ローンの残りはわずかだったにも関わらず、「あれ?団信じゃ足りない?」と思う出来事が起こりました。
父はすでに完済間近。ですが、万一に備えるつもりが「病気の種類によっては団信が出ない」ことや、「生活費が足りない」「相続した土地に税金がかかる」など、いろんな“想定外”が一気にのしかかってきたんです。
──そう、団信って「家のローン」は守ってくれるけれど、「家族の暮らし」までは守ってくれないんですよね。
今回は、そんな体験をもとに、団信だけでは守れない“もしも”に備える資産形成の考え方を一緒に掘り下げていきます💡
こんな方におすすめの記事です👇
- 住宅ローンを組んだばかりで「団信に入って安心」と思っている人
- 家族に何かあったときの備えが不安な人
- 住宅ローンと資産形成をどう両立するか悩んでいる人
【第1章】団信って何?住宅ローンとセットで語られる“安心神話”の正体
まず基本から整理しておきましょう。
団信(団体信用生命保険)とは、住宅ローン契約者が死亡または高度障害状態になったときに、ローン残高が保険金で完済される仕組みのことです。
つまり、家族が住み続けられるように、金融機関が“保険の力”でローンを帳消しにしてくれるというものですね🏠
✔団信の3つの基本ポイント
- 対象:死亡・高度障害が基本(+オプションでがん・三大疾病など)
- 加入:住宅ローンを組むときに必須 or 任意(フラット35など)
- 保険料:金利に含まれる場合が多い(別途支払いの場合もあり)
団信は基本的に「住宅ローンの残高=保険金」なので、いざというときの家計へのインパクトを減らせる仕組みです。
でも…ここに落とし穴があります。
📉団信の“安心神話”が招く誤解
「団信があるから、保険はいらないよね」
「団信に入ってるから、何があっても大丈夫だ」
──これ、実は大きな誤解なんです。
団信が守ってくれるのは“ローン”だけ。“家族の生活費”や“教育資金”などは対象外なんですね。
たとえば、子どもが小さい家庭では、万一のときに学費・生活費・医療費などが長期間かかることになります。
つまり「ローンはゼロになったけど、生活が苦しい」なんてことも起こりうるんです…。
📌豆知識:フラット35の団信は“任意加入”!
実は、フラット35を利用している場合、団信は任意です。つまり、加入していない人も意外と多いという落とし穴が!「入ってるつもりだったのに…」ということも。
📘用語解説:団体信用生命保険(団信)とは?
団信とは、住宅ローンの契約者が死亡や高度障害になった場合に、保険金で住宅ローンを完済する保険制度。ローン返済の保証人の代わりとして、金融機関が加入を求めることが多い。
💬カツくんの吹き出しコメント
カツくん:団信って“守ってくれる保険”だけど、あくまで「ローン」限定なんだよね~💦
万が一のとき、残された家族の生活費まで考えてないと、後から大変なことに…😱
【第2章】実はカバーされない団信の“盲点”とは?
さて、団信は住宅ローンの支払いをカバーしてくれる強力な保険…ですが。
「団信さえ入っていれば万全」というわけではありません。
ここからは、多くの人が見落としがちな“団信の盲点”について、具体例を交えて解説していきます。
🔍盲点①:病気でも“軽度”なら出ない!?
団信は基本的に「死亡」または「高度障害」が支払い対象です。
つまり、うつ病やがんの初期段階、あるいは仕事に支障が出る程度の持病などは、支払対象にならないことが多いんです。
例えば、以下のようなケースは“対象外”のことが多いです👇
- うつ病で長期休職 → 支払い対象外
- 初期のがん(治療可能) → 特約がなければ対象外
- 関節の手術や入院 → 高度障害に該当しなければ対象外
🔍盲点②:精神疾患・自殺は“免責期間”に注意
精神疾患が原因で死亡した場合、団信の保険金が支払われないケースがあります。
また、自殺についても加入から1年以内は対象外という「免責期間」があることが一般的です。
心の病は目に見えづらいぶん、制度面の理解がとても重要なんですね。
🔍盲点③:特約なしでは“がん・三大疾病”は対象外
最近では「がん団信」「三大疾病保障付団信」などのオプションも増えていますが、これは標準ではありません!
加入時に選択しないと、がんや心筋梗塞、脳卒中になってもカバーされないので要注意です。
💡ワンポイント:
「がん団信付きローン」と謳われていても、上皮内がんは支払い対象外のことも。契約内容をよく確認しましょう!
🔍盲点④:団信に通らない!?健康状態による審査落ち
住宅ローンの審査が通っても、団信の健康告知で“引っかかる”ケースがあります。
例えば、以下のような状況だと、加入できない or 割増保険料になる可能性があります👇
- 過去にうつ病の治療歴がある
- 糖尿病で通院中
- 手術歴がある(特に心臓・脳など)
その場合は「ワイド団信(緩和型)」を選ぶか、保険無しのフラット35などに切り替える必要があります。
📘用語解説:ワイド団信とは?
ワイド団信は、健康上の理由で通常の団信に加入できない人のために、告知項目を緩和した団信のこと。
通常よりも保険料が高くなるが、持病があっても加入しやすい。
🔍盲点⑤:完済しても“住まいリスク”は残る
たとえ団信でローンが完済されても、それで“家のリスク”がゼロになるわけではありません。
たとえば、こんなコストが今後も発生します👇
- 固定資産税
- リフォーム・修繕費
- 火災保険・地震保険の更新
住み続けるには生活費と住居費の両立が必要。団信=全ての問題解決ではないんですね。
💬カツくんの吹き出しコメント
カツくん:団信は「命と引き換えにローンがチャラになる」保険だけど、“生活の保障”まではカバーしてないってこと、ちゃんと知っておきたいよね💦
【第3章】“家は資産”のウソホント?ローンと資産形成の交差点
マイホームを買った人の多くが、どこかでこう考えます。
「この家も、将来は資産になる」
たしかに不動産は“資産”というカテゴリーに入りますが…本当にマイホームは資産形成につながるのでしょうか?
ここからは、「家=資産」という考え方の落とし穴と、住宅ローンが資産形成にどう関わるかを深掘りしていきます🏠💰
📉持ち家は“資産”だけど“流動性”が低い
確かに、家を持っていれば固定資産として価値はあります。
でも、いざお金が必要になったときに、すぐに売れますか?
場所によっては買い手がつかず、すぐに現金化できない…つまり“流動性が極端に低い”のがマイホームの特徴。
また、売却時には仲介手数料や登記費用、リフォーム費用などのコストがかかります。
📌NG例:「いざという時に売ればいい」は通用しない
住宅ローンの残債よりも売却価格が下回る“オーバーローン”状態だと、売っても借金が残るという事態に…。
💸家を買うと「資産形成の余力」が下がる?
住宅ローンの毎月返済+固定資産税+保険+メンテ費用などがかかると、毎月のキャッシュフローは確実に圧迫されます。
これにより、NISAや企業型DCへの積立が難しくなったり、投資に回す余力がなくなるケースも。
「家は買ったけど、老後の資産がゼロ…」というパターンも現実に多いのです。
📊住宅ローンと“人生3大支出”の関係
人生の三大支出といえば、以下の3つが有名ですね👇
- 住宅費
- 教育費
- 老後資金
住宅ローンに全力投球してしまうと、教育や老後への備えが疎かになる可能性が。
「人生のバランスシート」を作っておくことが、資産形成の第一歩になります。
📘用語解説:資産と負債のバランスとは?
資産とは「お金を生み出す・価値を持つもの(例:現金・株式・不動産)」、
負債とは「支払い義務のあるもの(例:住宅ローン・借入金)」を指します。
家は一見資産に見えても、ローンが残っているうちは「資産 - 負債 = プラスかマイナスか」が重要になります。
🏡家を“資産”に変える3つの視点
- 将来売却できる立地・構造にこだわる
→ 駅近・ハザードマップ確認・中古市場で流通があるかが鍵 - 住宅ローン返済計画にゆとりを持つ
→ ボーナス返済を前提にしない、ライフプランと照らし合わせる - “住まいも投資対象”と捉える
→ リフォームや二世帯化で価値を上げる視点も
💬カツくんの吹き出しコメント
カツくん:「家=資産」って思いがちだけど、実は“資産”か“負債”かは中身次第なんだよね💦
ちゃんと計画すれば、家だって立派な資産形成ツールになるワン🐾✨
【第4章】“もしもの備え”と家族の未来を守る3ステップ
ここまでで、団信だけでは守りきれない現実や、マイホームの資産性について見てきました。
では、実際にどう備えればいいのか?
この章では、“万が一”に備えながらも、将来に向けて資産形成を進める3つのステップをご紹介します。
🛡️ステップ①:「団信+生命保険」のバランスを取る
団信はあくまで住宅ローンの残債を守る保険。生活費や教育費をカバーするなら、別の備えが必要です。
おすすめは、必要最低限の生命保険で、遺族が数年間生活できる金額を確保すること。
📌必要保障額の考え方
- 年間生活費 × 遺族が生活する年数
- + 子どもの進学・教育資金
- - すでにある貯蓄や資産
これにより「万一のとき、子どもが大学に行けなくなる…」という事態を防ぐことができます。
📈ステップ②:NISAや企業型DCで“将来のお金”も備える
「今、もしもの備え」と「老後の生活費」は別物です。
だからこそ、資産形成を後回しにしないことが大事。
たとえば👇
- 企業型DC(確定拠出年金)で老後資金を自動積立
- 新NISAで、非課税枠を活かした長期運用
- 現金:投資=3:7のバランスで流動性を確保
団信や保険だけに頼らず、“働けるうちにお金を働かせる仕組み”を作っておくことが未来の安心に繋がります。
💬豆知識:保険と投資の違い
保険:万一に備える“守り”のお金(例:団信、医療保険)
投資:将来に向けた“攻め”のお金(例:株式、投資信託)
どちらも必要だけど、“何に備えるか”を明確にして分けることがポイント!
🧾ステップ③:“エンディングノート”で意志を可視化する
実は意外と盲点なのが、「自分がいなくなった後、家族が困らないように準備すること」です。
最近注目されているのが、エンディングノート。
財産の一覧や連絡先、加入している保険、ネット口座の情報などを整理しておくだけで、家族の負担をぐっと減らすことができます。
📌エンディングノートに書いておきたいこと
- 住宅ローンの残債や団信の種類
- 加入している保険と受取人
- 金融資産の一覧(NISA・DC・口座)
- 子どもへのメッセージ
「まだ早いかな」と思っていても、40代・50代は備えどき。元気なうちだからこそ、冷静に書けるんです。
💬カツくんの吹き出しコメント
カツくん:「保険だけ」でも「投資だけ」でも足りないワン!
“団信+生命保険+資産形成”の3本柱で、家族を守る安心な未来をつくろうね🐾✨
【まとめ】団信だけでは守れない。家と家族の未来に“本当の備え”を
今回は、「団信があれば安心」という考え方の落とし穴について、住宅ローンと資産形成の視点からお届けしました。
この記事のポイントをおさらいすると👇
✅本記事のまとめ
- 団信はあくまで「住宅ローンの残債」をカバーする保険である
- 生活費・教育費・老後資金は団信では守れない
- 持ち家は資産でありながら、流動性が低く“負債”にもなりうる
- 保険と資産形成の“両輪”があってこそ、本当の安心が生まれる
- エンディングノートや資産の見える化で、家族に安心を残せる
家を買ったときの“安心感”は、本当に素晴らしいものです。
でも、その安心を「本物の安心」にするためには──
もしもの備えと、未来へのお金の設計が必要です💡
住宅ローンを“負債”で終わらせるのか、“資産形成の一部”として活かすのか。
それを決めるのは、あなたのこれからの選択次第です。
👣今すぐできる行動リスト
- ✅ 自分の団信の補償内容を見直す
- ✅ 必要な生命保険の見直しをする
- ✅ NISAや企業型DCの積立額をチェック
- ✅ エンディングノートを書き始めてみる
あなたと、あなたの家族が、安心して暮らせる未来をつくるために──
今日がその第一歩になるかもしれません🏠✨
【カツくんの一言コーナー】
カツくん:団信って、安心の「第一歩」にはなるけど、それだけじゃ足りないワン!
「住宅ローン」+「もしもへの備え」+「未来の資産づくり」
この3つがそろって初めて、家族にとっての“ほんとの安心”になるんだよ🐾
無理なく少しずつ、できることから始めていこうワン!
【PR】団信を見直すなら、住宅ローンも見直すチャンス!
この記事でも紹介した通り、団信の内容は銀行によって全然違います。
もし「万一への備え」を本気で考えるなら、団信の保障が手厚い住宅ローンへの見直しも検討してみませんか?
▶ 住信SBIネット銀行の住宅ローンで“本当の安心”をつくる
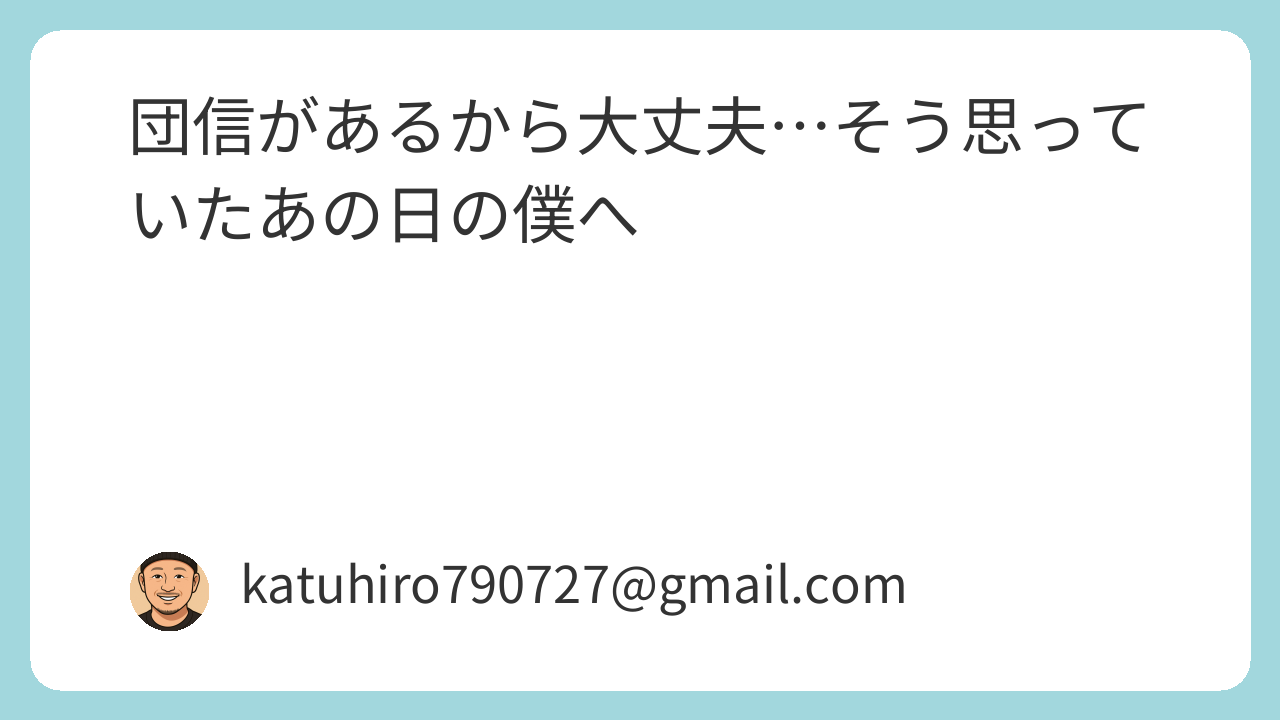
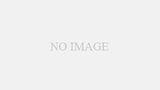

コメント