2023年末、ジュニアNISAが終了――。
子ども名義の非課税投資制度がなくなって、正直ちょっとショックでした。
「せっかく親子でお金を学ぶきっかけになってたのに…」
「もう子どもに投資を教える方法ってないのかな?」
そんな不安を持ったのは、きっと僕だけじゃないと思います。
でも安心してください。
新NISAが始まった今、ジュニアNISAの“代わり”以上にできることがあるんです📈
この記事では、我が家の経験をもとに、新NISAを活用した「親子投資教育」のリアルを紹介します。
📢カツくんのコメント
「制度が終わっても、“親子で学ぶ金融教育”は終わらない!
むしろ“ここからが本番”だよ〜📘✨」
第1章:「ジュニアNISAの終了」で起きた3つの変化
2023年末で終了したジュニアNISA。
制度終了により、親子投資に関する環境にもいくつか大きな変化がありました👇
① 新規投資ができなくなった(でも“運用”は継続可)
ジュニアNISAはすでに新規申込は停止。
しかし保有している資産は、引き続き非課税で運用可能です📊
売却・資金移動も自由にできるようになったため、より柔軟に活用できます。
② 「こども口座での投資」が制限され、親名義への依存が強まる
ジュニアNISAの代替制度がないため、未成年の資産運用は“親名義”での管理が基本になります。
そのため、親が管理者としての意識を持つことがますます重要に。
③ 「教育の機会」として活かす家庭と、やめてしまう家庭が分かれた
制度終了により、「もう子どもの投資はやめた」という家庭もあれば、
「むしろ新NISAで一緒に学び直そう!」という家庭もありました。
この違いを分けるのは、「お金を通して、何を伝えたいか」という家庭のスタンスだったと感じます。
📘用語解説:新NISAって何が変わったの?
2024年から始まった新NISAは、つみたて枠+成長投資枠の併用可能で、非課税保有限度額も1,800万円と大幅アップ!
“恒久化”されたことで、より長期目線の資産形成が可能に📈
第2章:新NISAを“親子の教育ツール”として使う方法
新NISAは「大人のための投資制度」と思われがちですが、
工夫すれば“親子で学ぶ教材”としてフル活用できます📚
ここでは、我が家で実践している“親名義の新NISA口座を使った教育法”をご紹介します。
① 一緒に「投資銘柄」を選ぶプロセスで会話を育てる
子どもが興味を持ちやすいテーマを選ぶのがコツです👇
- ディズニーや任天堂など、子どもが知ってる企業
- マクドナルド・コカコーラなど“身近な消費”をテーマにしたETF
- 動物・環境・未来技術など、興味のある分野に投資しているファンド
「この会社はどんなことをしている?」「そのサービスを使ったことある?」
そういった会話を重ねるだけで、子どもは“投資=難しい”という先入観から離れていきます。
② 投資履歴を「家族会議」で共有する習慣を作る
毎月1回、「資産がどう変化したか」を一緒に見る時間を作っています📊
例えば👇
- つみたてNISAで買ったファンドが、今月どうなったか?
- なぜ値上がりしたのか?下がったのは何が影響したのか?
これを「正解・不正解」でなく、「気づき・学び」として共有することで、
“投資=長期で考えるゲーム”という視点が育ちます。
③「実験口座」として一部を“子どもと一緒に決める”
我が家では、つみたてNISAの中で1〜2万円分だけ、子どもと相談して投資先を決めるようにしています。
もちろん、親が最終決定者です。でも、“選ばせてもらえた”という実感が、子どもにとっては大きな自信と好奇心になります。
📢カツくんのコメント
「“責任ある自由”を渡すって、教育ではめっちゃ大事だよね🧠✨
お金を通して、自分で選ぶ力も育つんだ!」
④ 利益が出たら「使い道を一緒に考える」イベントに
たとえば、「利益が出たらこの分を“ご褒美投資”にしよう!」というルールを作っておくと…👇
- 「この利益で何ができるかな?」
- 「貯めておく?使う?寄付する?」
という会話が生まれます。
“お金は目的ではなく手段”という価値観が自然に伝わるようになります✨
⑤ 経済ニュースを「親子で翻訳」して学ぶ
日経平均、FOMC、為替、インフレ、金利…
子どもには難しい用語も、生活にひもづけて会話すれば伝わります。
たとえば👇
「最近、お菓子が値上がりしてるのって知ってる?それは“インフレ”って言って…」
こんな具合に、経済を“生活のリアル”として学ぶきっかけにもなるんです。
第3章:親子投資に向く商品と、NGな商品選び
新NISAを使った親子投資教育では、どんな商品を選ぶかが学びの質を大きく左右します。
ここでは、我が家の実践や失敗も含めておすすめの商品タイプと、避けたい商品を紹介します📊
おすすめ①:インデックスファンド(全世界・米国株)
親子投資のスタートとして最もおすすめなのがインデックス型ファンドです。
中でも安定して人気なのは👇
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 楽天・オールカントリー株式インデックスファンド
世界経済やアメリカ市場を「まるごと買う」感覚があり、
子どもにも“地球規模で育てる”イメージが伝わりやすいです🌎
おすすめ②:身近なテーマに投資しているETF
子どもの興味にあわせて「ゲーム関連」「環境・クリーンエネルギー」「医療・ヘルスケア」など、
“好きなもの”に投資できるETFを一部に取り入れるのも有効です。
例えば👇
- QQQ(米国のハイテク株ETF)
- ICLN(再生エネルギー系)
- VHT(米国ヘルスケアETF)
「このETFの中にはどんな会社が入ってるの?」という会話が好奇心を刺激します。
避けたいNG商品①:レバレッジ型・高リスク商品
親子投資で絶対に避けるべきなのが、短期的な値動きの大きい商品。
- ブル型・ベア型のレバレッジETF
- ボラティリティの高い仮想通貨系商品
- IPO狙い・一発勝負の個別株
「ドカンと上がった!」「一瞬で半額に…」という体験は、
“投資=ギャンブル”という誤解を子どもに与えかねません⚠️
避けたいNG商品②:手数料が高すぎるアクティブファンド
アクティブファンドの中には信託報酬が年1.5〜2.0%を超えるものもあり、
長期投資としては“資産の成長を削る”リスクがあります。
「わかりにくい商品は買わない」
これが親子投資の“鉄則”です。
子どもに伝えるべき“選び方の基準”3つ
- ① 長く持てるか(10年以上)
- ② 値動きが激しすぎないか
- ③ 世の中に必要とされているか
この3つの視点があれば、子どもでも“いい投資・悪い投資”の感覚を育てられます。
📢カツくんのコメント
「“株は博打”って思われるの、ほとんどが“選び方”のミスなんだよね⚠️
“お金を育てる”ための商品かどうか、ちゃんと見極めよう💡」
第4章:親子投資で育つ“非認知能力”と、生きる力
投資教育というと、「お金の知識を教えること」だと思われがちですが、
実はそれ以上に“非認知能力(=テストで測れない力)”が育つのが大きなメリットです。
ここでは、親子投資を通じて育まれる“生きる力”の本質を見ていきましょう。
①「待つ力(我慢)」=複利を理解する土台
つみたて投資は、結果が出るまでに数年〜10年かかることもあります。
だからこそ、目先の変動では動じない“我慢力”が身につきます。
「今日より明日」「今より将来」
長期的に物事を見られる視点は、勉強にも、人間関係にも役立つスキルです。
②「自己肯定感」=選ばせてもらえる体験
「自分が選んだ商品が増えた!」
「話し合って決めた投資がうまくいった!」
そんな経験は、“自分の判断が認められた”という感覚につながります。
これは“自己肯定感の芽”になります。
投資は、“責任ある選択の積み重ね”だと教えられる絶好の教材なんです。
③「失敗を受け入れる力」=感情との向き合い方
投資には、必ず「うまくいかない時期」があります。
その時に、感情的に慌てるのではなく、原因を分析し、次の行動につなげる姿勢を持てるか。
親子で一緒に「なぜ下がったのか」「次にどうするか」を考えるプロセスは、
“人生でのつまずき”を乗り越える練習にもなります。
④「社会を見る力」=経済と生活のつながり
株価の動き、ニュース、インフレ、金利、為替…
投資に関わると、自然と“世界にアンテナ”が立つようになります。
「なんでスーパーの食材が高くなってるの?」
「戦争や災害は、経済にどんな影響があるの?」
そんな話題が日常の学びの場になっていきます🌍
⑤「親子の信頼関係」=一緒に学ぶから育つ絆
僕自身が一番感じているのはこれです。
「一緒に考える」「一緒に悩む」
このプロセスを重ねることで、子どもとの距離がぐっと近づきました。
親子投資は、「一緒に未来を描く時間」でもあるんです📈
📢カツくんのコメント
「“お金の教育”って実は、“生き方の教育”でもあるんだよね🌱
投資って、感情との向き合い・選択・継続、人生にそっくり!」
第5章:新NISA時代の親子投資まとめ|未来につながる家庭教育
ジュニアNISAは終わりました。
でも、親子で“お金を学び合う環境”は、むしろ今がスタート地点だと感じています。
新NISAは「親が学び、実践し、それを“会話”に変える」ための、最高の教育ツールなんです。
投資の目的は、決して「お金を増やすこと」だけではありません。
人生の選択肢を増やし、自由を得て、家族で未来を描けること。
これこそが“親子投資”の真の価値ではないでしょうか?
親子投資を成功させるための3つのポイント
- ① 親がまず「楽しんで学ぶ」姿勢を見せること
- ② 難しい言葉は使わず、「体験ベース」で伝えること
- ③ お金を通して、信頼と対話を育てること
これらを意識すれば、たとえ制度が変わっても、
家庭という“小さな投資学校”は、きっと続けていけるはずです🏡📘
まとめ:制度が終わっても、“学び”は終わらない
・ジュニアNISAは終了したけれど、親のNISAを活かせば親子投資は可能
・銘柄選び・資産変動・利益の使い道など、すべてが教育の素材
・選択力・我慢力・社会を見る目など、“非認知能力”も育つ
・親子で“同じ未来”を考えることが信頼と絆を深める
制度ではなく、「関わり方」こそが学びになる。
今日からでもできる、小さな投資教育を家庭から始めてみませんか?
🎤カツくんの一言コーナー
「制度が終わっても、“学ぶ気持ち”に終わりはないよね✨
投資って、人生の縮図。
子どもと一緒に“増える喜び”も“下がる悔しさ”も体験できたら…それはもう、最高の教育だよ📈😊」
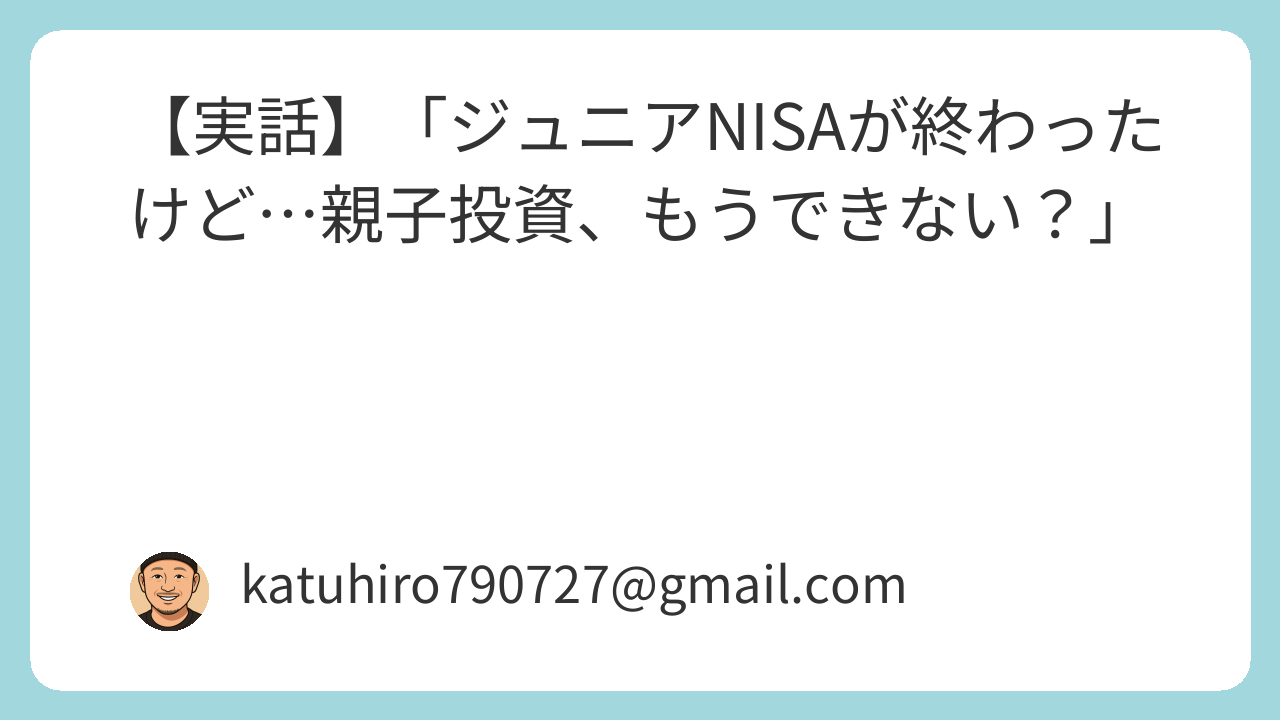
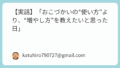

コメント