「パパ、これ買ってもいい?」
ある日、3歳の息子が、スーパーでおもちゃのついたお菓子を見つめながら、僕にそう聞いてきました。
たしかに、買ってあげられる。値段も数百円です。
でも僕の頭にはふと、こんな言葉がよぎりました。
「“お金を与える”ことはできても、“お金を育てる力”は教えられているか?」
今、日本では金融教育が叫ばれています。
だけど、学校ではまだまだ不十分。
ならば家庭で「お金の教養」をどう育てるかが、これからの時代を生きる子どもたちにとって重要なテーマだと僕は感じています。
そんなときに出会ったのが「ジュニアNISA」。
この制度を通して、僕たち親子は“お金を増やす”体験を一緒に始めることができました。
📢カツくんのコメント
「子どもに“節約しなさい”って言う前に、大人が“増やす背中”見せられるかが勝負だよね📈✨」
- 第1章:なぜ今、“親子でお金を学ぶ”必要があるのか?
- 第2章:ジュニアNISAが教えてくれた“お金の増やし方”
- 第3章:家庭でできる!「親子投資教育」のリアルな実践例
- 第4章:よくある誤解&NG例(タブー・ありがちな失敗)
- 第5章:子どもと一緒に育つ資産形成と“親の成長”
- まとめ:今からでも遅くない!家庭教育が未来の資産になる
- 🎤カツくんの一言コーナー
- 【実話】「ジュニアNISAが終わったけど…親子投資、もうできない?」
- 第1章:「ジュニアNISAの終了」で起きた3つの変化
- 第2章:新NISAを“親子の教育ツール”として使う方法
- 第3章:親子投資に向く商品と、NGな商品選び
- 第4章:親子投資で育つ“非認知能力”と、生きる力
- 第5章:新NISA時代の親子投資まとめ|未来につながる家庭教育
- まとめ:制度が終わっても、“学び”は終わらない
- 🎤カツくんの一言コーナー
第1章:なぜ今、“親子でお金を学ぶ”必要があるのか?
昔は「お金の話なんて子どもにするもんじゃない」と言われていましたよね。
でも今はまったく逆。お金の話をしないことのほうが“リスク”になっている時代です。
なぜなら、こんな社会背景があるからです👇
- 終身雇用が崩れ、「給与だけで一生安泰」ではない
- 年金不安・増税・インフレなど、将来予測が難しい
- “投資が当たり前”な世代になる子どもたち
- にも関わらず、学校教育では「貯金止まり」な内容が多い
つまり、お金の正しい知識と感覚を家庭で伝えることが、一番リアルで生きた教育になるんです。
家庭でのお金教育=「日常の中にあるリアルな教材」
我が家では、「お金は大切にね」ではなく、「お金をどう動かすか?」をテーマにしています。
たとえばこんな場面でも👇
- ポイント還元の仕組みをゲーム感覚で話す
- お釣りの計算を一緒にする
- 「この100円を、1年後に120円にできたら?」と仮想シナリオを話す
こうした会話の積み重ねが、「お金=増やせるもの」という視点を自然に育ててくれると感じています。
親も一緒に学ぶ姿を見せるのが最大の教育
親が「難しい」「自分は無知だから」と諦めていたら、子どももお金を“難しいもの”と感じてしまいます。
僕自身も以前は、レバレッジ商品やパチンコ依存で失敗したこともあります💦
だからこそ、「一緒に学ぼう」という姿勢が、信頼感と学びの土壌をつくると思っています。
📘用語解説:ジュニアNISAとは?
ジュニアNISAは、未成年の子ども名義で非課税の投資口座を作れる制度。
2023年で新規受付は終了しましたが、2024年以降も口座運用・売却は可能です。
教育資金の準備や、親子の金融教育に使う家庭が増加中📊
第2章:ジュニアNISAが教えてくれた“お金の増やし方”
僕がジュニアNISAを始めたのは、「将来の教育資金を少しでも増やせたら」という思いからでした。
でも実際にやってみると、それだけではなく、親としても“お金の見方”が変わる大きなきっかけになったんです。
“預ける”から“育てる”へ:お金との付き合い方が進化
これまで僕は、貯金=正義と思っていました。
「貯めておけば安心」「通帳の残高が多いほうが正しい」と。
でもジュニアNISAを通じて、「お金には働いてもらえる」という感覚が身につきました。
たとえば、年間80万円を非課税で運用できる環境があると、
投資信託を通して世界経済に触れるきっかけになります。
「この投資信託はどの企業に投資してるの?」「日本だけじゃなく海外も含まれるの?」「なぜ米国株の割合が多いの?」
そんな疑問が、親子の会話にも自然と反映されてくるんです。
増やすこと=「ギャンブル」ではない。計画的な仕組み化
僕は昔、投資=ギャンブルだと思っていました。
FXや仮想通貨に短期集中で手を出しては損失…そんな過去があります😓
でもジュニアNISAでは、インデックス投資という“堅実な資産運用”を選びました。
- 全世界株式インデックス
- S&P500連動型ファンド
- つみたて分散型商品(年率4〜7%想定)
こうした商品は、一発当てることを目的にしていません。
長期・分散・積立によって資産をじっくり育てる。
その姿勢が、親としても子どもに伝えたいスタンスだったのです。
📢カツくんのコメント
「“お金はすぐに増やすものじゃない”。これって、家庭教育の“我慢”とか“継続”とも似てるよね📚」
子どもに伝えたい「時間を味方につける力」
ジュニアNISAの最大の魅力は、「非課税で長期保有できる」という時間の味方です。
そしてそれは、まさに人生にも通じる考え方だと思うんです。
「すぐに結果を求めない」「コツコツ続ける」「複利の力を信じる」
これって、勉強・習い事・人間関係にも応用できる考え方ですよね。
僕は息子に、「時間の使い方次第で人生は変わる」ということを、投資を通して少しずつ伝えていきたいと思っています。
“自分名義の資産”という感覚が、将来の責任感を育てる
まだ息子は3歳で、当然ジュニアNISAの意味なんてわかっていません。
でも、小学校・中学校と成長する中で、「このお金は自分の未来のために投資されている」という感覚が芽生えたら…
「自分には大切なものを託されている」
そんな意識が、お金の責任感・自己肯定感・未来への意識を育ててくれると僕は信じています。
第3章:家庭でできる!「親子投資教育」のリアルな実践例
「お金の話を子どもにどう教えればいいのか分からない」
そう思う親御さんはとても多いです。
でも実際には、日常の中にヒントや教材はたくさんあります。
ここでは、我が家で実際に行っている“親子の投資教育ごっこ”を、リアルな例とともにご紹介します👇
① 絵本や図鑑から“お金の世界”へ導入
まずは子ども向けの絵本やマンガを活用。
たとえば👇
- 『おかねのかいかた えほん』(こども向け投資入門)
- 『マンガでわかる!14歳からのお金入門』
- 『おしりたんてい おこづかい事件簿』←意外と金銭教育ネタあり
これらを寝る前の読み聞かせにしたり、「お金ってどうやって生まれるの?」とクイズ感覚で話すと、自然に“経済”の入口が開きます📖
②「ポイント=ミニ投資体験」ゲームで学ぶ
我が家では、買い物をするときに「何%ポイントがつくか」を一緒に計算して遊んでいます。
- 「この200円のお菓子、5%ポイントっていくら?」
- 「10回買ったらポイントだけで何円?」
たったそれだけでも、“お金は使ったあとにも戻ってくる可能性がある”という感覚が身につきます。
③「ジュニアNISA口座の資産を、定期的に“見る”習慣」
毎月1回、子どもと一緒にNISA口座の状況を見て、「増えたね!」「ちょっと下がったけど、これは長期だから大丈夫」と“感情込みの会話”をしています。
たとえばグラフを見せながらこう言います👇
「この上がり下がりを“ジェットコースター”にたとえたらどう思う?」
子どもは「落ちたときもワクワクしたらいいのか〜」と返してくる。
そんな体感を通じた教育が、もっとも記憶に残ります🎢
④「お金に名前をつける」ゲーム
1,000円札を見ながら、「これは何に使う1,000円?」と名前をつけさせる遊び。
たとえば👇
- 「これは“未来を育てる1,000円”」(投資)
- 「これは“楽しい時間を買う1,000円”」(映画や外食)
- 「これは“ありがとうを伝える1,000円”」(プレゼント)
お金は「価値を交換する道具」という本質を学ぶきっかけになります。
⑤「親も自分の投資口座を見せる」オープンな姿勢
恥ずかしさもありますが、親自身のNISAやiDeCo、保有資産を見せて会話することも意識しています。
「これがパパの“老後のお金”になる部分だよ」
「この株は、みんなが好きなコンビニを運営してる会社だよ」
そんな風に話すと、投資が遠い話じゃなくなるんです。
📢カツくんのコメント
「“資産”って言葉より、“お金の畑”って言い方すると子どももワクワクするよ🌱“育てる”って感覚が伝わるからおすすめ〜」
第4章:よくある誤解&NG例(タブー・ありがちな失敗)
「親子で投資教育って素晴らしい!」…確かにその通りですが、
やり方を間違えると“逆効果”になるリスクもあります💦
ここでは、実際に僕自身がやりかけた・または周囲で見かけた、ありがちなNG例を紹介します👇
NG①:「お金の話=成功体験だけ」を押しつける
「これだけ増えた!」「資産○○万円になったよ!」
そんな話ばかりをしてしまうと、子どもは“成功しないと価値がない”という誤解を抱くことがあります。
むしろ大切なのは、うまくいかなかった体験も含めて共有すること。
僕は、昔FXやレバ商品で失敗したことも息子に話すつもりです。
「うまくいかなかったことから学ぶ姿勢」こそ、教育の本質だと思うからです。
NG②:「投資の話ばかり」になってしまう
家庭内で「株がどうこう」「今月の成績が…」と投資が話題の中心になると、
子どもは“お金がすべて”という偏った価値観を持ってしまう可能性があります。
大切なのは、“お金は手段”であり、“目的”ではないということを伝えること。
そのためにも、お金以外の会話や遊び、自然体験も一緒に大切にするバランス感覚が必要です。
NG③:「子どもに任せきり」「教えっぱなし」
「子どもの口座だから、好きにやらせていいや」
「一度話したから、あとは覚えてるでしょ」
こんな“丸投げ教育”は危険です⚠️
投資やお金のことは、繰り返し&対話を通じて育つもの。
“積立と同じように、教育も積み上げ式”だと心得ましょう💡
NG④:「まだ早い」「うちの子は理解できない」
これはもっとも多い誤解です。
子どもは「難しい話」よりも「体感・ゲーム・絵本」から学ぶのが得意です。
早すぎることはありません。
むしろ、“小さな気づき”を積み重ねた子どもこそが、真の金融リテラシーを身につけると感じています。
📘ワンポイント:NG例を“学びのチャンス”に変えるには?
失敗をしたら、一緒に振り返る。
「じゃあ次はどうすればいい?」と“再設計”する過程が、最高の教育時間になります📚
NG⑤:「親がやってないのに、子どもにだけ期待」
これ、僕が実は一番反省したことです。
自分は家計管理や資産形成が中途半端なのに、
「子どもにはちゃんと学ばせたい」と思っていた時期がありました。
でも、子どもは“言葉”より“親の背中”を見て育ちます。
親が変われば、子も自然に変わる。
“教える前に、自分が学ぶ”ことが、一番の近道でした。
📢カツくんのコメント
「教育って“やり方”じゃなくて“あり方”だよね🌱
自分の姿を見て“お金の姿勢”を感じ取ってくれるのが、一番うれしい瞬間かも✨」
第5章:子どもと一緒に育つ資産形成と“親の成長”
ジュニアNISAを通じた親子の金融教育。
実は子どもの成長と同じくらい、親自身も成長するものだと僕は実感しています。
僕も昔は、浪費やギャンブル、短期売買にハマっていた時期がありました。
でも今は、「子どもに誇れる資産形成をしたい」と思うようになり、行動も変わってきました。
- 積立投資をやめずに継続できるようになった
- 節約の視点が「我慢」ではなく「選択」に変わった
- 家族との会話に“お金の話”が自然に溶け込むようになった
“家庭の投資教育”は、親のマインドセットを変える最強のスイッチだったのです。
資産形成=「お金」ではなく「選択肢」を増やすこと
子どもにお金の話をするとき、僕はこう伝えるようにしています。
「お金は、君の未来の“選べる自由”を増やしてくれる道具だよ」
だからこそ、正しく付き合える力=金融リテラシーが必要。
そしてその種は、家庭という“毎日の教室”で、親と一緒に育てていけるのです。
まとめ:今からでも遅くない!家庭教育が未来の資産になる
ジュニアNISAは終了した制度ですが、「親子でお金を学ぶきっかけ」としては今も大きな価値があります。
そして、これからは新NISA、つみたて投資、教育費対策…
あらゆる資産形成が“親の選択”に委ねられていく時代です。
だからこそ、今こそ家庭の中で「お金って何だろう?」「どう使うといいのかな?」という会話を始めてみてください。
お金=タブーではなく、未来の可能性。
親子で学ぶこのプロセスこそが、何よりの財産になるはずです✨
🎤カツくんの一言コーナー
「“投資”って、株式や信託だけじゃなくて、
“子どもと話す時間”にも投資なんだよね。
1日10分でもいい。将来、大きく育つ資産になるよ💡
今日から始めよっか📘✨」
【実話】「ジュニアNISAが終わったけど…親子投資、もうできない?」
2023年末、ジュニアNISAが終了――。
子ども名義の非課税投資制度がなくなって、正直ちょっとショックでした。
「せっかく親子でお金を学ぶきっかけになってたのに…」
「もう子どもに投資を教える方法ってないのかな?」
そんな不安を持ったのは、きっと僕だけじゃないと思います。
でも安心してください。
新NISAが始まった今、ジュニアNISAの“代わり”以上にできることがあるんです📈
この記事では、我が家の経験をもとに、新NISAを活用した「親子投資教育」のリアルを紹介します。
📢カツくんのコメント
「制度が終わっても、“親子で学ぶ金融教育”は終わらない!
むしろ“ここからが本番”だよ〜📘✨」
第1章:「ジュニアNISAの終了」で起きた3つの変化
2023年末で終了したジュニアNISA。
制度終了により、親子投資に関する環境にもいくつか大きな変化がありました👇
① 新規投資ができなくなった(でも“運用”は継続可)
ジュニアNISAはすでに新規申込は停止。
しかし保有している資産は、引き続き非課税で運用可能です📊
売却・資金移動も自由にできるようになったため、より柔軟に活用できます。
② 「こども口座での投資」が制限され、親名義への依存が強まる
ジュニアNISAの代替制度がないため、未成年の資産運用は“親名義”での管理が基本になります。
そのため、親が管理者としての意識を持つことがますます重要に。
③ 「教育の機会」として活かす家庭と、やめてしまう家庭が分かれた
制度終了により、「もう子どもの投資はやめた」という家庭もあれば、
「むしろ新NISAで一緒に学び直そう!」という家庭もありました。
この違いを分けるのは、「お金を通して、何を伝えたいか」という家庭のスタンスだったと感じます。
📘用語解説:新NISAって何が変わったの?
2024年から始まった新NISAは、つみたて枠+成長投資枠の併用可能で、非課税保有限度額も1,800万円と大幅アップ!
“恒久化”されたことで、より長期目線の資産形成が可能に📈
第2章:新NISAを“親子の教育ツール”として使う方法
新NISAは「大人のための投資制度」と思われがちですが、
工夫すれば“親子で学ぶ教材”としてフル活用できます📚
ここでは、我が家で実践している“親名義の新NISA口座を使った教育法”をご紹介します。
① 一緒に「投資銘柄」を選ぶプロセスで会話を育てる
子どもが興味を持ちやすいテーマを選ぶのがコツです👇
- ディズニーや任天堂など、子どもが知ってる企業
- マクドナルド・コカコーラなど“身近な消費”をテーマにしたETF
- 動物・環境・未来技術など、興味のある分野に投資しているファンド
「この会社はどんなことをしている?」「そのサービスを使ったことある?」
そういった会話を重ねるだけで、子どもは“投資=難しい”という先入観から離れていきます。
② 投資履歴を「家族会議」で共有する習慣を作る
毎月1回、「資産がどう変化したか」を一緒に見る時間を作っています📊
例えば👇
- つみたてNISAで買ったファンドが、今月どうなったか?
- なぜ値上がりしたのか?下がったのは何が影響したのか?
これを「正解・不正解」でなく、「気づき・学び」として共有することで、
“投資=長期で考えるゲーム”という視点が育ちます。
③「実験口座」として一部を“子どもと一緒に決める”
我が家では、つみたてNISAの中で1〜2万円分だけ、子どもと相談して投資先を決めるようにしています。
もちろん、親が最終決定者です。でも、“選ばせてもらえた”という実感が、子どもにとっては大きな自信と好奇心になります。
📢カツくんのコメント
「“責任ある自由”を渡すって、教育ではめっちゃ大事だよね🧠✨
お金を通して、自分で選ぶ力も育つんだ!」
④ 利益が出たら「使い道を一緒に考える」イベントに
たとえば、「利益が出たらこの分を“ご褒美投資”にしよう!」というルールを作っておくと…👇
- 「この利益で何ができるかな?」
- 「貯めておく?使う?寄付する?」
という会話が生まれます。
“お金は目的ではなく手段”という価値観が自然に伝わるようになります✨
⑤ 経済ニュースを「親子で翻訳」して学ぶ
日経平均、FOMC、為替、インフレ、金利…
子どもには難しい用語も、生活にひもづけて会話すれば伝わります。
たとえば👇
「最近、お菓子が値上がりしてるのって知ってる?それは“インフレ”って言って…」
こんな具合に、経済を“生活のリアル”として学ぶきっかけにもなるんです。
第3章:親子投資に向く商品と、NGな商品選び
新NISAを使った親子投資教育では、どんな商品を選ぶかが学びの質を大きく左右します。
ここでは、我が家の実践や失敗も含めておすすめの商品タイプと、避けたい商品を紹介します📊
おすすめ①:インデックスファンド(全世界・米国株)
親子投資のスタートとして最もおすすめなのがインデックス型ファンドです。
中でも安定して人気なのは👇
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 楽天・オールカントリー株式インデックスファンド
世界経済やアメリカ市場を「まるごと買う」感覚があり、
子どもにも“地球規模で育てる”イメージが伝わりやすいです🌎
おすすめ②:身近なテーマに投資しているETF
子どもの興味にあわせて「ゲーム関連」「環境・クリーンエネルギー」「医療・ヘルスケア」など、
“好きなもの”に投資できるETFを一部に取り入れるのも有効です。
例えば👇
- QQQ(米国のハイテク株ETF)
- ICLN(再生エネルギー系)
- VHT(米国ヘルスケアETF)
「このETFの中にはどんな会社が入ってるの?」という会話が好奇心を刺激します。
避けたいNG商品①:レバレッジ型・高リスク商品
親子投資で絶対に避けるべきなのが、短期的な値動きの大きい商品。
- ブル型・ベア型のレバレッジETF
- ボラティリティの高い仮想通貨系商品
- IPO狙い・一発勝負の個別株
「ドカンと上がった!」「一瞬で半額に…」という体験は、
“投資=ギャンブル”という誤解を子どもに与えかねません⚠️
避けたいNG商品②:手数料が高すぎるアクティブファンド
アクティブファンドの中には信託報酬が年1.5〜2.0%を超えるものもあり、
長期投資としては“資産の成長を削る”リスクがあります。
「わかりにくい商品は買わない」
これが親子投資の“鉄則”です。
子どもに伝えるべき“選び方の基準”3つ
- ① 長く持てるか(10年以上)
- ② 値動きが激しすぎないか
- ③ 世の中に必要とされているか
この3つの視点があれば、子どもでも“いい投資・悪い投資”の感覚を育てられます。
📢カツくんのコメント
「“株は博打”って思われるの、ほとんどが“選び方”のミスなんだよね⚠️
“お金を育てる”ための商品かどうか、ちゃんと見極めよう💡」
第4章:親子投資で育つ“非認知能力”と、生きる力
投資教育というと、「お金の知識を教えること」だと思われがちですが、
実はそれ以上に“非認知能力(=テストで測れない力)”が育つのが大きなメリットです。
ここでは、親子投資を通じて育まれる“生きる力”の本質を見ていきましょう。
①「待つ力(我慢)」=複利を理解する土台
つみたて投資は、結果が出るまでに数年〜10年かかることもあります。
だからこそ、目先の変動では動じない“我慢力”が身につきます。
「今日より明日」「今より将来」
長期的に物事を見られる視点は、勉強にも、人間関係にも役立つスキルです。
②「自己肯定感」=選ばせてもらえる体験
「自分が選んだ商品が増えた!」
「話し合って決めた投資がうまくいった!」
そんな経験は、“自分の判断が認められた”という感覚につながります。
これは“自己肯定感の芽”になります。
投資は、“責任ある選択の積み重ね”だと教えられる絶好の教材なんです。
③「失敗を受け入れる力」=感情との向き合い方
投資には、必ず「うまくいかない時期」があります。
その時に、感情的に慌てるのではなく、原因を分析し、次の行動につなげる姿勢を持てるか。
親子で一緒に「なぜ下がったのか」「次にどうするか」を考えるプロセスは、
“人生でのつまずき”を乗り越える練習にもなります。
④「社会を見る力」=経済と生活のつながり
株価の動き、ニュース、インフレ、金利、為替…
投資に関わると、自然と“世界にアンテナ”が立つようになります。
「なんでスーパーの食材が高くなってるの?」
「戦争や災害は、経済にどんな影響があるの?」
そんな話題が日常の学びの場になっていきます🌍
⑤「親子の信頼関係」=一緒に学ぶから育つ絆
僕自身が一番感じているのはこれです。
「一緒に考える」「一緒に悩む」
このプロセスを重ねることで、子どもとの距離がぐっと近づきました。
親子投資は、「一緒に未来を描く時間」でもあるんです📈
📢カツくんのコメント
「“お金の教育”って実は、“生き方の教育”でもあるんだよね🌱
投資って、感情との向き合い・選択・継続、人生にそっくり!」
第5章:新NISA時代の親子投資まとめ|未来につながる家庭教育
ジュニアNISAは終わりました。
でも、親子で“お金を学び合う環境”は、むしろ今がスタート地点だと感じています。
新NISAは「親が学び、実践し、それを“会話”に変える」ための、最高の教育ツールなんです。
投資の目的は、決して「お金を増やすこと」だけではありません。
人生の選択肢を増やし、自由を得て、家族で未来を描けること。
これこそが“親子投資”の真の価値ではないでしょうか?
親子投資を成功させるための3つのポイント
- ① 親がまず「楽しんで学ぶ」姿勢を見せること
- ② 難しい言葉は使わず、「体験ベース」で伝えること
- ③ お金を通して、信頼と対話を育てること
これらを意識すれば、たとえ制度が変わっても、
家庭という“小さな投資学校”は、きっと続けていけるはずです🏡📘
まとめ:制度が終わっても、“学び”は終わらない
・ジュニアNISAは終了したけれど、親のNISAを活かせば親子投資は可能
・銘柄選び・資産変動・利益の使い道など、すべてが教育の素材
・選択力・我慢力・社会を見る目など、“非認知能力”も育つ
・親子で“同じ未来”を考えることが信頼と絆を深める
制度ではなく、「関わり方」こそが学びになる。
今日からでもできる、小さな投資教育を家庭から始めてみませんか?
🎤カツくんの一言コーナー
「制度が終わっても、“学ぶ気持ち”に終わりはないよね✨
投資って、人生の縮図。
子どもと一緒に“増える喜び”も“下がる悔しさ”も体験できたら…それはもう、最高の教育だよ📈😊」


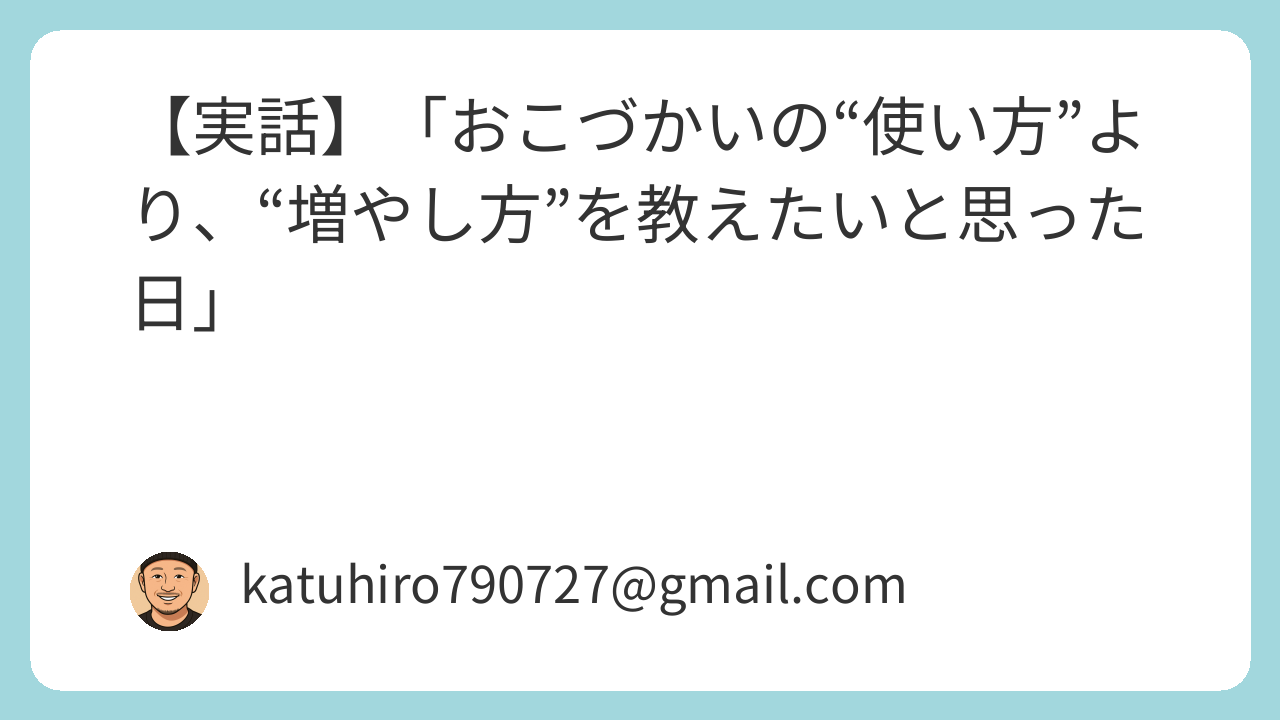
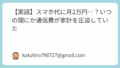

コメント